「こころの病気」での障害年金の特徴
(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など)
「こころの病気」の場合には、他の病気と比べて、以下のような特徴があります。
以下、内容について、順番にご説明をさせていただきます。
(1)診断書を作成する医師との関係がとても大切となる
 「こころの病気」の場合に、障害年金が受給できるかは、診断書の「日常生活の状況の項目」の記載内容がポイントとなります。
「こころの病気」の場合に、障害年金が受給できるかは、診断書の「日常生活の状況の項目」の記載内容がポイントとなります。
「日常生活の状況」とは、日常の家事(食事、清潔保持、買い物・外出など)にどの程度の制限があるかということです。
この「どの程度の制限があるか」については、検査の数値などと違い、明確な基準があるわけではありません。
また、医師が、「日常生活の状況」について、細かくカルテに記録しているとは限りません。
そのために、他の病気と比べて、診断書を取得する前に、医師に「日常生活の状況」について、十分に伝えておくことがとても大切となります。
また、障害年金には、審査の基準(障害認定基準)が定められています。
そして、診断書を記載する医師(精神科、心療内科の医師)は、「障害認定基準」を十分に把握しているのが通常です。
これに対して、他の病気で障害年金の申請をする場合、診断書を作成する医師(精神科、心療内科以外)は、必ずしも「障害認定基準」を把握しているとは限らないといえます。
このことは、他の病気で障害年金を申請する場合との大きな違いといえます。
別の言い方をすれば、診断書を作成する精神科や心療内科の医師は、どのような診断書ならば障害年金を受給できるか、把握している場合が多いといえます。
このような事情から、障害年金の申請にあたっては、医師とよく相談し、申請自体についての理解を事前に得ておくことが大切となります。
また、診断書の取得前に、症状や日常生活などの詳しい状況を伝えておくことが重要となるのです。
以上のように、「こころの病気」での障害年金の申請の場合には、医師との関係が、他の病気での申請の場合に比べて、格段に大切になります。
そのため、日頃から、医師とのコミュニケーションを十分に取ることが必要とされるのです。 もし、自分では、医師とのコミュニケーションを取ることが難しい場合には、家族の方の協力を得て、家族からも医師に必要な情報を伝えることが大切となります。
(2)働きながら障害年金を受けられるか(就労と障害年金の関係)
「こころの病気」の場合、「障害年金は一般の会社などで働いていると受けられないのではないか」との質問を受けることがあります。
結論から先にいうと、障害年金は一般の会社などで就労しているからといって、受給することができないわけではありません。
実際、働きながら、障害年金を受給している方はたくさんいらっしゃいます。
当センターの最近の事例(一般の会社で週4日・1日7時間のアルバイト勤務を長期にわたって継続しているケース)でも、障害等級2級に認定され、障害年金を受けることができています。
ただし、「こころの病気」の場合、「就労しているか」、「就労の内容」については、障害年金の審査の上での重要な評価項目になっていて、審査結果に大きな影響があります。
この点は、他の病気で障害年金の申請をする場合との大きな違いです。
繰り返しとなりますが、単に一般の会社などで働いているからといって、障害年金を受けられないというわけではありません。
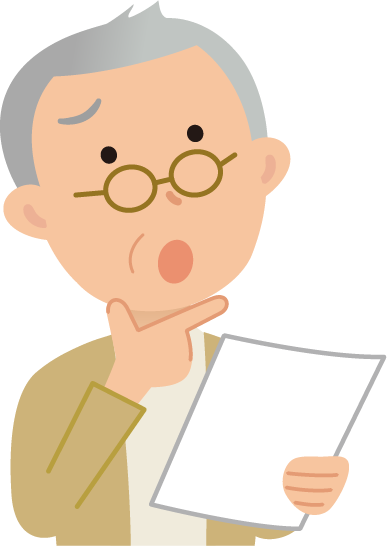 問題となるのは、「労働の質と量」です。
問題となるのは、「労働の質と量」です。
言いかえれば、「どのような仕事を、どのくらいやっていて、働く上でどのような制限・支障があるか」ということが問題となるのです。
そのために、障害年金の診断書の取得にあたっては、医師に対して、就労の内容や就労の状況(就労の困難さなど)を詳しく伝えておくことがとても重要になります。
もう少し具体的に説明をすると、次のとおりです。
例えば、「就労の内容」については、勤務日数、就労時間のほか、軽い事務仕事なのか、他人とのコミュニケーションを伴わない仕事なのか、単調なルーティンワークなのかの点などを含め、仕事の内容を医師によく説明するということです。
また、「就労の状況(就労の困難さなど)」については、実際の勤務の状況(体調の悪化により、休みを取ったり、勤務を中断することがないのか、職場の同僚などから受けているサポートの内容など)を医師に十分に説明するということです。
そして、大切なことは、伝えた具体的内容を、医師に診断書の中に記載をしてもらうということです。
また、「病歴・就労状況等申立書」の中でも、「就労の内容や状況」を詳しく記載していくことが必要となります。
例えば、職場での周りからの援助の状況、仕事中や仕事の終了後の状態、職場での出来事などを含めて、就労の困難さを詳しく説明していくのです。
このような内容をわかりやすく記載することが必要となるため、「こころの病気」の場合には、この「病歴・就労状況等申立書」の役割や位置づけが、他の病気に比べて、一層重要なものとなります。
最後になりますが、単に、一般の会社などで働いているから、自分で無理だと考え、また、まわりから申請しても年金が出ないと言われて、障害年金の申請をしないことはとても残念です。
障害年金の申請にあたって大切なことは、「就労の内容」や「就労の状況(困難さ)」を診断書や病歴・就労状況等申立書などで詳しく伝えることにあります。
この点をよく念頭に置いて、障害年金の申請を進めていくことが、「こころの病気」の場合には、何より大切となります。
(3)障害年金受給のメリットは大きいが、自分で申請すると負担が大きく大変
「こころの病気」の場合、他の病気と比べて、障害年金を受給できた場合のメリットが大きいといえます。
一つは、障害年金を過去にさかのぼって申請する場合についてです。
(初診日から1年6か月経過時点までさかのぼって申請する場合です。)
 過去にさかのぼって障害年金の受給が認められた事例を見ると、その多くの場合は、「こころの病気」での障害年金の申請の場合となっています。
過去にさかのぼって障害年金の受給が認められた事例を見ると、その多くの場合は、「こころの病気」での障害年金の申請の場合となっています。
そして、過去にさかのぼって障害年金を受給する場合、年金の初回の振込額がとても高額になります。(特に障害厚生年金の場合)
また、初診日が20歳前で、20歳の時点から障害年金をずっと受給できるケースも、ほとんどの場合「こころの病気」の場合となっています。
しかし、メリットが大きい分、障害年金の申請にあたっては、越えなければならないハードルも高いといえます。申請内容が複雑なケースも多くあります。
そのため、障害年金の申請にあたっては、事前の準備を含めて、慎重に手続きを進めることが必要となります。また、ポイントを踏まえた申請を行うことも大切です。
このような障害年金の申請を、「こころの病気」の場合、初めから終わりまで、すべて自分で申請をすることは、通院などの状況を考えると、大きな負担と困難を伴います。
例えば、「初診日」をいつの時点とするかについて、難しい判断が必要となるケースがあります。
また、診断書の依頼する際にも、正確な内容の診断書を取得するため、日常生活の状況などを詳しく書面にまとめて、医師に手渡すことなどが必要になります。
さらに、自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」についても、他の病気の場合と比べて、日常生活や就労の状況などを詳しく記載することが求められます。
そのため、書くべき内容も多くなり、作成には多くの時間がかかり、かなりの負担となります。
このように、すべてを一人でやり遂げるには、大きな負担や困難を伴うことになります。
そのため、家族のサポートを受けたり、障害年金の受給に向けて、専門家に相談してみることも必要になります。





